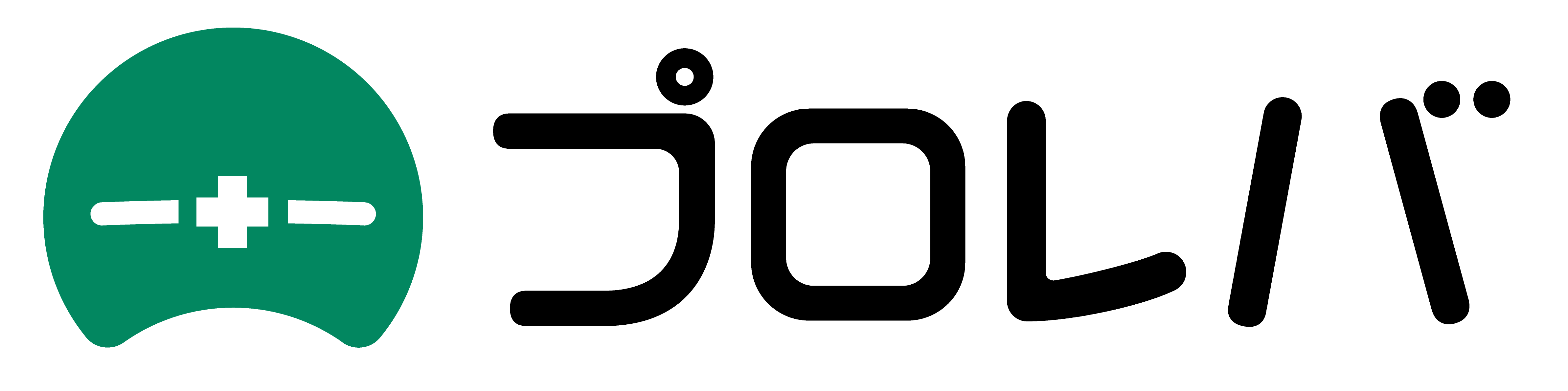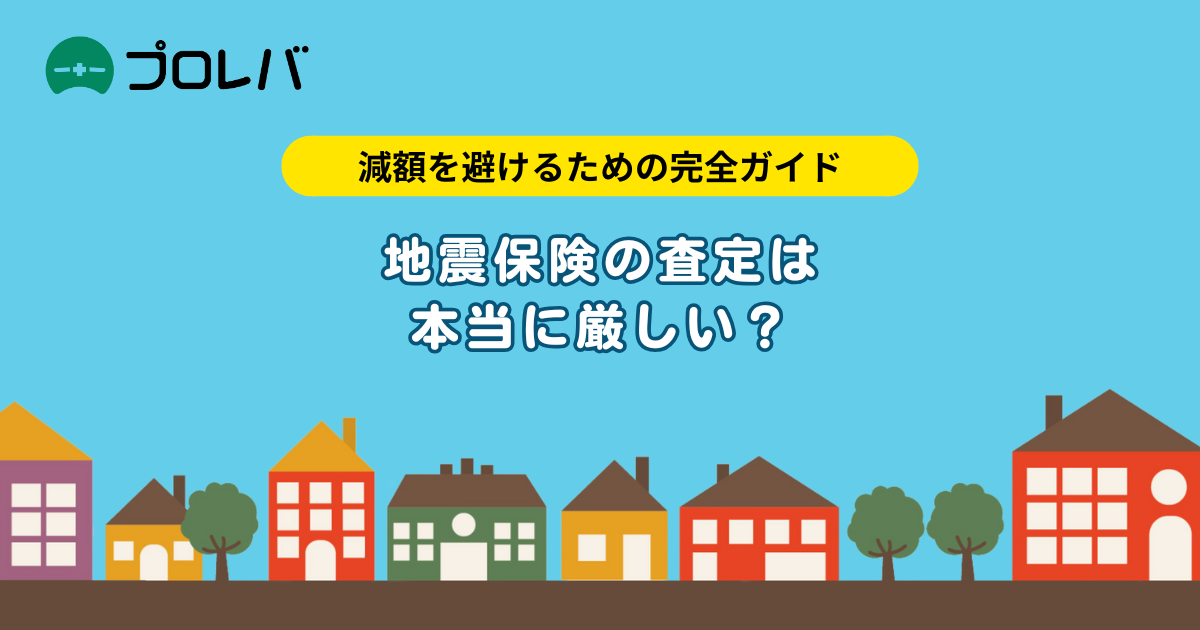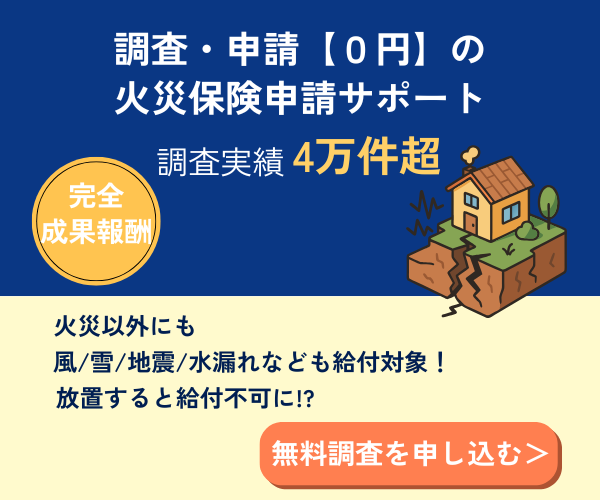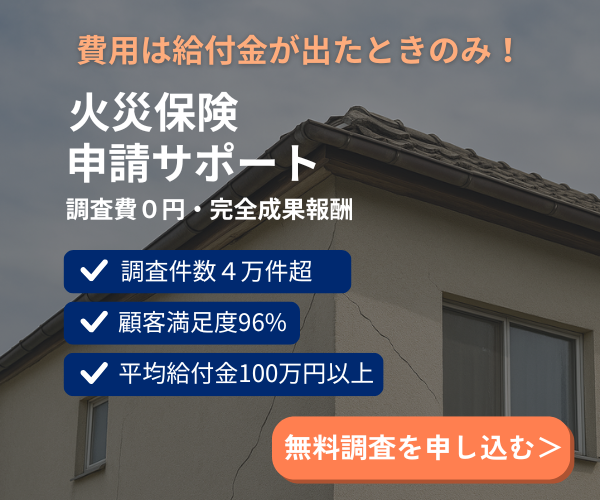大地震で住まいに被害を受けても「思ったより保険金が下りなかった」「査定が厳しくて非該当になった」と悩む声は少なくありません。本記事では、なぜ査定が厳しいのかを明らかにし、適正に保険金を受け取るための準備・証拠集め・再調査のポイントをわかりやすく解説します。
地震保険の仕組みと査定の全体像
地震保険の査定を理解するためには、まず「そもそもどんな仕組みで運用されているのか」を知っておくことが大切です。火災保険に付帯して契約するのが基本で、建物や家財の損害を対象にしています。ただし、認定区分や補償範囲には明確なルールがあり、これを知らずに申請すると「思ったより保険金が出ない」という結果につながりやすいのです。ここでは査定の全体像を整理して、理解の土台をつくっていきましょう。
地震保険とは?
地震保険は単独では契約できず、火災保険に付帯して加入する仕組みになっています。
対象:主要構造部(基礎や柱、壁、屋根など)
対象外:門・塀・車両など
補償される災害:地震や噴火、津波を原因とする災害
台風や大雨なども補償する火災保険とは異なり、地震保険は災害や対象が狭まります。
認定区分(全損・大半損・小半損・一部損)の基礎
地震保険の査定では、被害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階で評価します。全損なら契約金額の100%、大半損は60%、小半損は30%、一部損は5%といった形で支払額が決まります。
※損保ジャパン公式
よくある誤解:経年劣化・地震以外の要因は原則対象外
査定時に誤解が多いのが、経年劣化や他の自然災害による被害との区別です。古い家のひび割れや沈下などは地震が直接の原因でないと判断されることが多く、補償対象外となります。また、台風や大雨による損害は地震保険ではなく火災保険での対応が原則です。この線引きを知らずに申請すると「なぜ補償されないのか」と疑問を抱きやすくなるため、事前に理解しておくことが欠かせません。
地震保険の査定が厳しいと感じる理由

地震保険の査定が厳しいとは一概には言い切れません。査定は
・震度
・調査する鑑定人の判断
で決まります。
震度の小さい地震で、大きな被害が出るとは考えられません。そのため、ご自宅に被害があるように見受けられても、震度4以上の地震がないと、認められないこともあります。
調査に来る鑑定の判断で地震保険の査定が決まる
調査に来る鑑定人は保険会社から依頼を受けて調査を行います。公平な立場で調査しているとは思いますが、あくまでも保険会社側の立ち位置であることには変わりありません。また、人間が調査するため、見落としがある可能性もあります。
地震保険は補償範囲が火災保険と比べて断定的であるため、厳しいと感じる人も多いのでしょう。

地震保険の厳しい査定をクリアするには
査定結果に満足いかない場合は大きく3つの方法があります。
追加書類を提出する
被害箇所が地震保険(火災保険)の補償範囲であることを説明できる資料を用意し、追加で提出することで再調査してもらえる可能性が上がります。
保険会社のお客様センターに相談する
各保険会社にはお客様窓口が設置されているケースがあります。まずは、お客様センターに相談することがやりやすいと思います。
| 保険会社名 | 電話番号 |
|---|---|
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 0120-721-101 |
| アクサ損害保険株式会社 | 0120-449-669 |
| イーデザイン損害保険株式会社 | 0120-063-040 |
| AIG損害保険株式会社 | 0120-016-693 |
| SBI損害保険株式会社 | 0800-8888-836 |
| 共栄火災海上保険株式会社 | 0120-719-112 |
| ジェイアイ傷害火災保険株式会社 | 0120-532-200 |
| セコム損害保険株式会社 | 0120-333-962 |
| ソニー損害保険株式会社 | 0120-101-656 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 0120-668-292 |
| 大同火災海上保険株式会社 | 0120-671-071 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 0120-071-281 |
| 日新火災海上保険株式会社 | 0120-17-2424 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 0120-288-861 |
| 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 0120-312-770 |
| 明治安田損害保険株式会社 | 0120-255-400 |
| 楽天損害保険株式会社 | 0120-115-603 |
「そんぽADRセンター」に相談する
また、「そんぽADRセンター」という相談センターもあります。「そんぽADRセンター」とは日本損害保険協会(損害保険全体を管轄する団体)が運営しております。ご相談や苦情・紛争解決手続にかかる費用は原則として無料ですし、中立的な立場で相談にのっていただける窓口のため、安心して利用できます。
火災保険申請サポートに相談する
保険申請に慣れていないお客様自身が申請しても払い渋られたりする可能性もあります。
プロレバはこれまで4万件以上の調査を行ってきました。平均給付金も約100万円で、お客様自身で気が付かなかった被害箇所も特定してより多くの給付金を手にすることも可能です。
火災保険・地震保険の申請は被害から3年以内に行うのが原則です。3年を過ぎると経年劣化と判断される可能性もありますのでご注意ください。
査定の見られ方を理解する|評価ポイントの内訳
査定がどのような基準で行われるのかを理解していないと、「なぜこの金額なのか」と納得できない結果になりがちです。実際の査定では、建物の部位ごとに損傷の程度を評価し、一定の割合や基準値を満たすかどうかで認定区分が決まります。ここでは、査定で注目される評価ポイントと、再調査によって覆る可能性があるケースを整理しておきましょう。
構造・部位別の損傷割合と閾値(壁・基礎・屋根・内装など)
地震保険の査定では、建物全体を一括で評価するのではなく、壁・基礎・屋根・内装といった部位ごとに損傷の程度がチェックされます。例えば、壁のひび割れや屋根瓦のズレが「全体の一定割合」を超えているかどうかで損害区分が変わります。閾値(しきいち)を下回ると「軽微」と判定されやすく、申請者が感じる被害の深刻さと査定結果にズレが生じるのです。
「一部損」認定のハードルと減額のよくある理由
査定で最も多いのが「一部損」の認定です。契約金額の5%しか支払われないため、実際の修繕費に比べて「少なすぎる」と感じる人が多くなります。減額の典型例としては、損傷が全体の基準割合に届かないケースや、複数の部位に被害があっても個別に見ると「軽微」と判定される場合です。このように査定は基準に忠実である一方、被害者目線では厳しく感じられるのが実情です。
再調査(セカンドオピニオン)で覆るポイント
一度下された査定結果も、再調査で覆ることがあります。特に写真の不足や原因特定の不明確さが理由で減額された場合、追加の証拠や専門家による調査報告を提出することで認定区分が変わるケースは少なくありません。例えば、基礎のひびが経年劣化とされたものが「地震特有のひび」と再判定され、支払額が増えることもあります。査定は絶対ではなく、適切な準備をすれば結果を改善できる余地があるのです。
地震保険の申請は自分で行うべき?
地震保険の申請は、必ずしも専門家に頼まなければならないわけではありません。被害の状況や契約内容を正しく理解できていれば、自力で十分に対応できるケースも多くあります。ただし、損害の範囲が広い場合や原因の特定が難しい場合には、専門家に依頼することで認定額が大きく変わる可能性があります。ここでは、自力で行うか専門家に任せるかの判断基準を整理します。
自力で十分なケース(軽微でも証拠が明瞭・契約把握済み)
ひび割れや瓦のずれなど被害が限定的で、写真や被害メモで十分に証拠を残せる場合は、自力申請で問題ないことが多いです。また、自分の契約内容(建物・家財の補償範囲、免責額など)を正確に把握していれば、誤った申請を避けられるため、スムーズに進められます。
専門家を使うべきケース(構造・原因特定が難しい場合)
基礎のクラックや壁のひびなど、地震か老朽化か判別が難しい場合は専門家の調査が有効です。また、複数の部位に被害がある場合や、被害の因果関係を整理しなければならない場合も、専門家に依頼することで認定されやすくなります。特に「初回査定で非該当」「減額されて納得できない」というケースでは、再調査を専門家と一緒に行うのが効果的です。
専門家を使うときの注意点
専門家への依頼費用は「完全成功報酬型」で30〜40%程度が相場とされています。依頼時には「着手金の有無」「成功報酬の上限」「調査範囲」「追加請求の可能性」などを必ず確認しましょう。また、過度に高い報酬率を提示する業者や契約内容が不透明な業者は避けるべきです。契約前に見積と契約書をしっかり確認することで、トラブルを防ぎつつ安心して依頼できます。
プロレバは成果報酬型で、業界最安値の給付金の28%(税別)が手数料です。給付金が下りなければ手数料がかからないため、気軽にご相談いただけます。
FAQ|よくある質問と短答
地震保険の査定に関しては、多くの人が同じような疑問や不安を抱えています。ここでは、よくある質問に対して簡潔に答えをまとめました。細かな部分は契約や状況によって異なりますが、基本的な考え方を押さえておくことで、迷わず行動できるようになります。
余震で悪化した場合は?「発生ごとの記録」が有効
余震によって損傷が広がった場合でも、記録があればその分を含めて申請できます。被害が拡大した時点で再度写真を撮影し、どの地震でどの被害が生じたのかを整理しておくことが重要です。
古い家は不利?評価の見方と立証で変わる余地
築年数が古い家は「経年劣化」と判断されやすい傾向がありますが、必ずしも不利とは限りません。過去の写真や施工記録と比較して「地震直後に新たに生じた損傷」であることを示せば、認定される可能性は十分にあります。
一度非該当になったら終わり?再申請・再調査の現実
初回で非該当とされた場合でも、追加の証拠や専門家の報告を提出すれば再調査で認められることがあります。特に「写真不足」や「原因特定の不明確さ」が理由の場合、再申請で結果が変わるケースは少なくありません。
家財のみ/賃貸の場合のポイントは?
地震保険は建物と家財が別契約になっているため、賃貸住宅に住んでいる人は「家財のみ」を対象に加入していることが多いです。この場合、家具・家電・衣類などが補償対象となります。契約時に家財金額の上限を確認し、想定する生活再建に十分かどうか見直すことが大切です。
このチェックリストをフル活用することで、「やるべきことが分からない」という不安を解消し、スムーズに査定対応ができるはずです。
まとめ
地震保険の査定は確かに厳格で、利用者の感覚と査定結果にギャップが生じやすい仕組みです。しかし、事前準備や証拠の残し方、見積の工夫によって「納得できる査定結果」を引き出すことは十分可能です。大切なのは、厳しさを嘆くのではなく、制度のルールを理解したうえで「どうすれば適正に受け取れるか」を考える姿勢です。